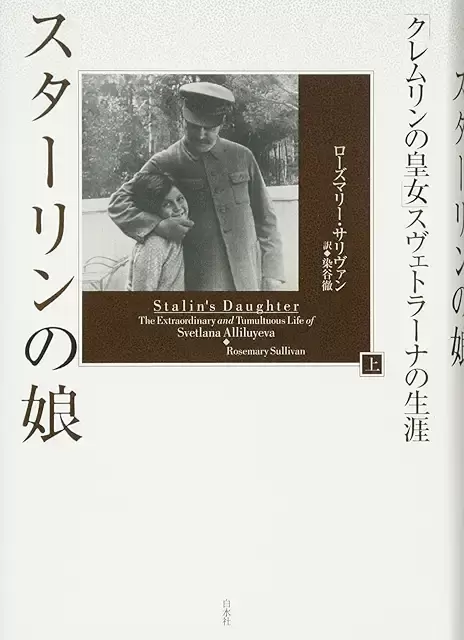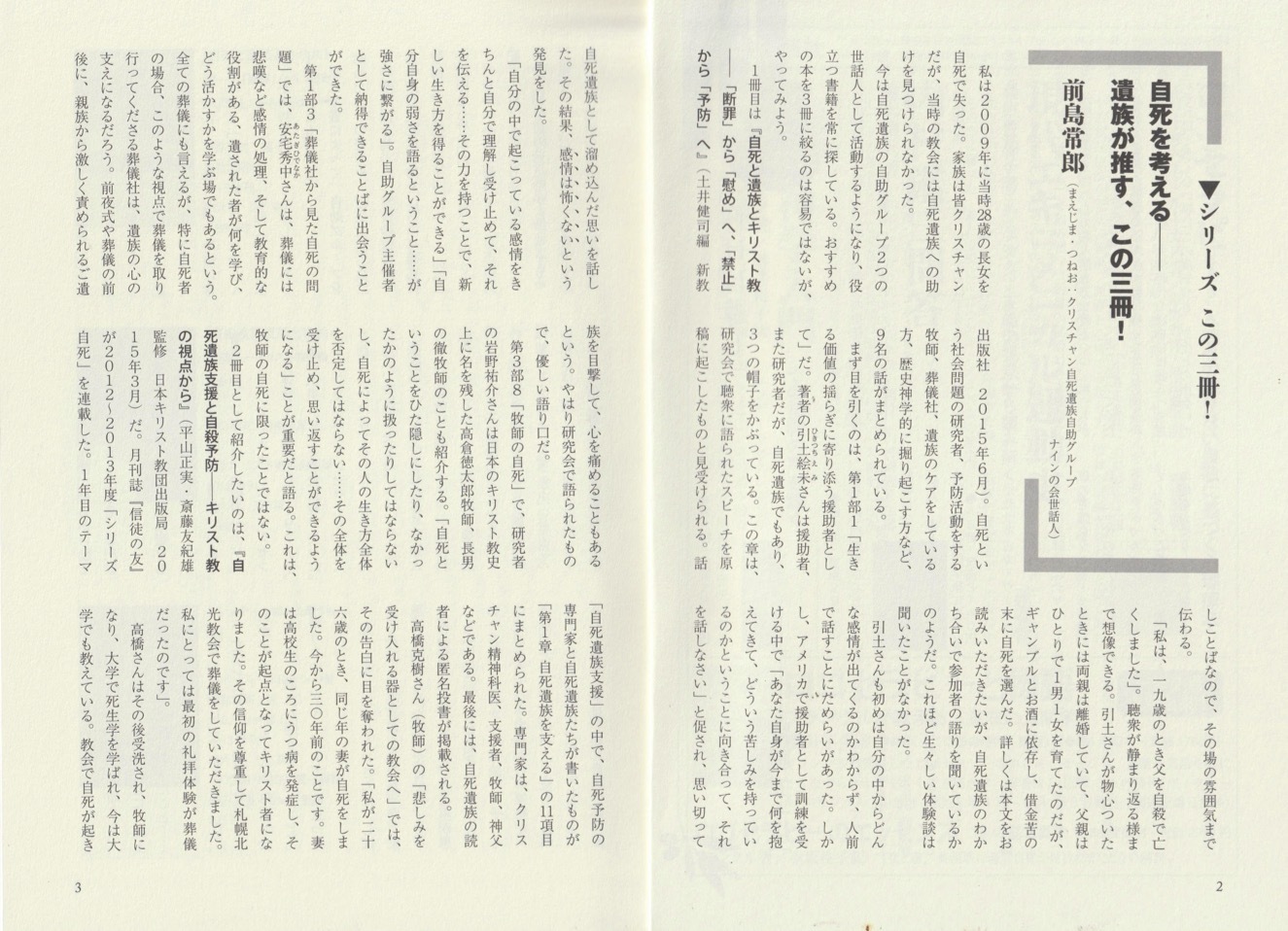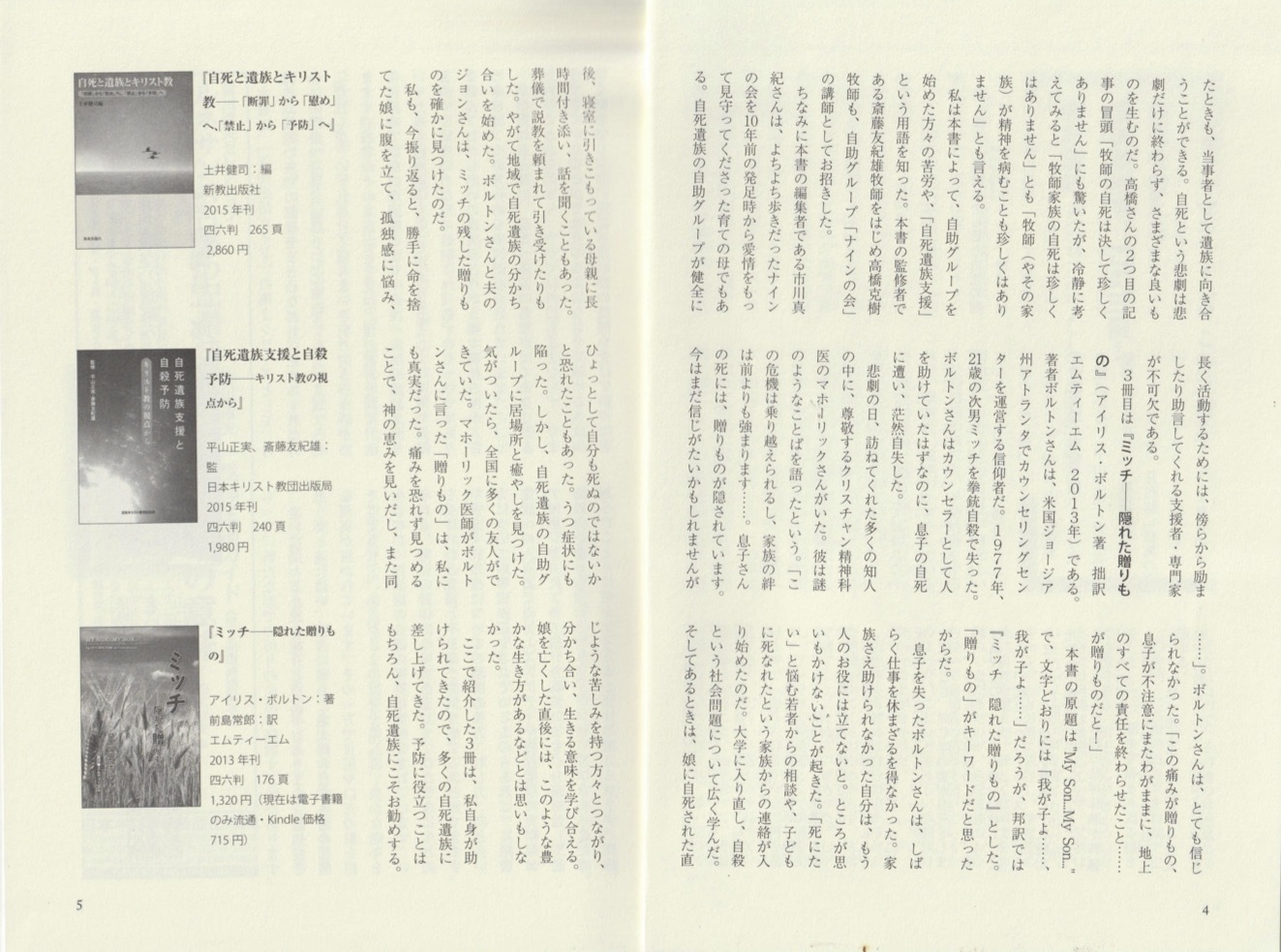12月31日
72歳の歳を終える。
祖父が70を超えた時は、ずいぶん爺さんだなと思ったものだが、
私もやはり爺さんです。(なんだそりゃ?)
今年の夏頃でしたか、もう10年以上会っていない知人からメールがありました。
彼はエクアドルに住んでいる人で(多分アメリカ人)、前は同じ団体で仕事仲間
でしたが、今は全く違うところで働いている。
「ボイス・オブ・ザ・マーターズ(殉教者の声)」と言う団体で、出版物があるのだけれど
その日本語訳をしないかという。
ただし、紙の印刷をするというのではなく、ネット上で無料閲覧するものだ。
できないことではないので協力することにしたが、その内容には驚くことばかり。
クリスチャンであるというだけで、命を狙われるところが世界には多くある。ローマ
帝国時代の話ではなく、21世紀の話である。そのような迫害を受けている(人権侵害
とも言える)人々の実話を世界の教会に知らせ、祈り援助しようという意図である。
日本でキリスト教はメジャーではなく、クリスチャンは人口のコンマ何%しかいない。
完全に無視されている。むしろ「何かの信仰を持っている」と言えば、「洗脳されてる、
あわれだな」と思われてしまう国である。
生きにくさはあるものの、命の危険を感じたことはない。
ところが、共産圏、イスラム教圏では、文字通りに命の危険を冒してキリスト教信仰を死守
している方々が今もいる。「お前にそれだけの覚悟があるか」と問われれば、返事につまる。
400ページにもなろうという本の翻訳レビューを、まもなく終えようとしている。
来年も新しい企画に協力する予定だ。